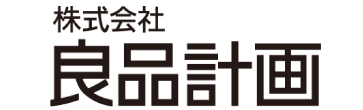公益財団法人 セゾン文化財団
日本の現代演劇・舞踊の振興、およびその国際交流の促進に寄与するため、助成活動を行っています。
TOPICS
イベント森下スタジオアーカイブ配信のご案内:「次世代の芸術創造を活性化する研究助成」2024年度助成対象事業報告会
2025年9月11日に開催いたしました報告会「地域文化を支える仕組みの30年を振り返る――これまでの議論をこれからの実践につなげるために必要な基盤とは?」のアーカイブ映像を公開しております。ぜひご覧ください。
また、当日ご参加の皆さまに配布した資料も、下記リンクより併せてご参照いただけます。
「地域文化を支える仕組みの30年を振り返る――これまでの議論をこれからの実践につなげるために必要な基盤とは?」
※視聴期限:20025年12月17日
当日配布資料
https://drive.google.com/file/d/1lk-WbvrUNWWduNvUECaWpfqCk6hOM5r6/view?usp=sharing
また、今後のプログラムや報告会を充実させていくため、アンケートへのご協力をお願いできれば幸いです。(想定時間:5分)
「次世代の芸術創造を活性化する研究助成」 2024年度助成対象事業報告会
地域文化を支える仕組みの30年を振り返る
これまでの議論をこれからの実践につなげるために必要な基盤とは?
セゾン文化財団では、2024年度の次世代の芸術創造を活性化する研究助成の報告会を開催します。助成対象者の一般社団法人associations/地域と文化と制度の研究会のメンバーによる活動報告と、舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM)の小野江麻里子氏をゲストに迎えたディスカッションを実施します。
報告者:佐藤 李青、小川 智紀、田中 真実、戸舘 正史、上地 里佳 地域と文化と制度の研究会
ゲスト:小野江 麻里子 舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM)
日時:2025年9月11日(木)18:00-19:45
会場:森下スタジオ(東京都江東区森下3-5-6:都営新宿線、大江戸線「森下駅」 A6出口徒歩5分)
定員:15名
参加:無料(事前申込制)
申込方法:ご参加をご希望の方は以下のリンクからお申込みください。
https://www.saison.or.jp/250911debriefing/register
※後日、アーカイブ配信も実施いたしますので、アーカイブ配信のご視聴を希望の方も上記のリンクからお申込みください。
報告会概要
この数十年で、地域を舞台とした文化事業が増え、その中間支援の仕組みも広がってきました。アートNPOやアーツカウンシルなどで現場を支える “現場” の担い手は、個々の事業に伴走し、よりよい実践へと後押しするため、さまざまな工夫や取り組みを重ねています。活動同士を横断的につなげたり、現場の環境を整備・改善したりと、各地で試行錯誤が続けられています。
では、その担い手にとって必要な共有知とは何なのだろうか。日々の実践の足元を支え、新たな担い手へのバトンになるような考え方。それを探るために、わたしたちは歴史をたどり、理念をふりかえることが、ひとつの方法になるのではないかと考えました。今回はリサーチを通じて出会ったキーワードを軸にディスカッションの場をひらきます。(地域と文化と制度の研究会)
一般社団法人associations/地域と文化と制度の研究会
中間支援の立場で地域の芸術文化活動にかかわってきたメンバーが、それぞれが携わっている現場から見えてくる課題や理念について研究会や読書会、フィールドリサーチ等を通じて議論を行っている。2025年8月、地域と文化をめぐる思考と実践とプラットフォーム「region」を開設準備中。

佐藤 李青 (アーツカウンシル東京 プログラムオフィサー)
多様な主体の連携により、地域の文化事業を実践する東京アートポイント計画やTokyo Art Research Lab、東京都・区市町村連携事業などを担当。Art Support Tohoku-Tokyo(東京都による芸術文化を活用した被災地支援事業)には立ち上げから終了まで携わる。2011年6月より現職。単著『震災後、地図を片手に歩きはじめる』(アーツカウンシル東京、2021年)、共著『文化政策の現在』(東京大学出版会、2018年)ほか。一般社団法人associations 代表理事。

小川 智紀 (認定NPO法人STスポット横浜 理事長、社会福祉士、社会教育士)
2004年、STスポット横浜の地域連携事業立ち上げに参画し2014年より理事長。現在、横浜市芸術文化教育プラットフォーム事務局、ヨコハマアートサイト事務局を行政などと協働で担当。またNPO法人アートNPOリンク理事・事務局長として、厚生労働省障害者芸術文化活動普及支援事業の連携事務局を担当。NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク理事。NPO法人子どもと文化全国フォーラム理事。「子ども白書」編集委員。愛知大学、跡見学園女子大学非常勤講師。

田中 真実 (認定NPO法人STスポット横浜 事務局長・副理事長)
1984年東京生まれ。お茶の水女子大学卒業、東京工業大学大学院社会理工学研究科修了。2008年STスポット横浜入職。文化施設や芸術団体と学校現場をつなぐ横浜市芸術文化教育プラットフォーム事務局、地域文化をサポートするヨコハマアートサイト事務局、障害福祉と芸術文化をつなぐ神奈川県障害者芸術文化活動支援センターを行政などと協働で運営。NPO法人アートNPOリンクスタッフ。NPO法人アクションポート横浜理事。

戸舘 正史(アートマネジメント、文化政策)
公共ホール、美術館、中間支援機関などでの勤務を経て 2018年から2023年まで愛媛大学社会共創学部寄附講座「松山ブンカ・ラボ」ディレクター。みなと芸術センター研究機能専門参与、港区文化芸術活動サポート事業調査員、小金井市芸術文化振興計画推進委員会委員長、都民芸術フェスティバル(音楽部門)外部評価員などを務める。日本文化政策学会会員。四国学院大学非常勤講師。共著『芸術と環境』(論創社、2012)、『アートはいつアートになるのか(仮)』(水曜社、2025年秋刊行予定)など。

上地 里佳(沖縄アーツカウンシル チーフプログラムオフィサー)
1988年沖縄県宮古島市生まれ。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、2013年東京アートポイント計画「三宅島大学」のアートマネージャーとして携わる。2014年より富山県氷見市を拠点とするアートNPOヒミングのアートマネージャーとして、市民とアーティスト、行政との協働のかたちを模索しながら、アートプロジェクトの現場運営を担う。2016年からはアーツカウンシル東京にて、東京アートポイント計画、Tokyo Art Research Labを担当。2021年より現職。
ゲスト

小野江 麻里子(舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM)事務局長)
2006~17年PARC – 国際舞台芸術交流センターにてTPAM in Yokohamaプログラム・オフィサーとして国際プラットフォーム事業に携わる。舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM)の設立に参加し、2013年より事務局長として従事。2019年4月〜2025年3月まで理事長兼事務局長。2009年文化庁新進芸術家海外研修制度研修員としてエジンバラ、ロンドンに滞在。認定NPO法人STスポット横浜、特定非営利活動法人国際舞台芸術交流センター、公益社団法人 全国公立文化施設協会、公益財団法人現代人形劇センター理事。文化庁文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議委員。
2026年度公募プログラム オンライン説明会
はじめて申請を予定している方、久しぶりの申請を検討されている方に向けた説明会です。募集内容や申請書交付に関する概要および手続きについてご説明後、ご質問にもお答えします。
セゾン・フェロー(I・II 共通)募集要項読み合わせ会&質問会
読み合わせ会第1回:2025年8月7日(木)11:00-11:30
読み合わせ会第2回:2025年8月14日(木)19:00-19:30
質問会:2025年8月19日(火)19:00-19:30
※第1回と第2回は同内容です。ご都合のつく日程でご参加ください。
創造環境イノベーション
2025年8月12日(火)14:00-14:30
研究助成
2025年8月13日(水)19:00-19:30
海外リサーチ活動支援
2025年8月6日(水)19:00-19:30
お申し込み方法
以下のフォームに必要事項をご記入の上、お申し込みください。
オンライン説明会お申し込みフォーム
ヴィジティングフェローによるトーク 2/5(水)@森下スタジオ
身体に刻み込む——傷と証言 (Marking the body: wound and witness)

インドのアーメダバードを拠点に活動するパフォーマンス・アーティストで、「Conflictorium (Museum of Conflict :紛争のミュージアム)」等での活動を通じて紛争や分断に創造的な方法で橋を架けることを目指してきたアヴニー・セティ氏によるトークを開催いたします。セティ氏がこれまでにおこなったパフォーマンスや、携わってきたプロジェクトのコンセプト・実際の取り組みについて紹介します。
「このトークでは、インド・グジャラート地方の心理社会的な地形によって形作られた、“記憶の場所”として、そして“証言”としての身体について語ります。私のパフォーマンス実践では、暴力の歴史や集合的な記憶が宿る場所を探求し、身体を媒体として、記憶と忘却、破裂と修復の間にある緊張関係を読み解きます。
このような、異なるナラティブが交錯し、沈黙が共有される場所の中で、私の実践は公道、教室、舞台といった個人的・集合的な歴史が交わる空間において展開されます。振付の探求と身体的な実践を通じて、身体を“記録を刻む場”であり、かつ“抵抗の手段”として捉え、トラウマと回復力(レジリエンス)の交差点を描き出します。
今回は、集団的な内省の場を提供し、パフォーマンスをキュレーション的な行為として捉えます。時には、既存の動きの枠組みを問い直すことを通じて、歴史、記憶、つながりの可能性、そして再生について親密かつ公的に向き合う機会となるでしょう。(アヴニー・セティ)」
イベント概要
日時:2025年2月5日(水) 19:00-20:30
会場:森下スタジオ
登壇者:アヴニー・セティ
※日英逐次通訳
※定員15名
※要申込
■アーカイブ動画
登壇者のプロフィール等の詳細は以下をご覧ください。
https://www.saison.or.jp/vf2024_avnisethi
主催:公益財団法人セゾン文化財団
※「助成事業に係る広報活動やネットワーク構築」の一環として本報告会を実施します。
舞台芸術AiRミーティング2024
国内外の舞台芸術の関係者との出会いやネットワーク、情報交換の機会の創出を目的とするミーティング。国内のアーティスト・イン・レジデンスの滞在アーティストやプロデューサーをゲストに招いて、AiRから生まれた作品やプロジェクトの事例を紹介します。
日時:2024年12月14日(土)11:00-11:40
場所:横浜市開港記念会館(横浜市中区本町1丁目6−6)
※上記イベントへのご参加にはYPAM参加登録(プロフェッショナル)が必要となります。
プレゼンテーション1
世田谷美術館×アートネットワーク・ジャパン「Performance Residence in Museum」
2023-24 滞在アーティスト 藤原佳奈によるプレゼンテーション
『XXの身体』~女性の身体にまつわるフィクションの再編~
内容:藤原佳奈を中心としたコレクティブ・プロジェクト〈松のにわ〉の企画。人形遣い、俳優、精神保健福祉士、生物学研究者、舞台美術家、ダンサーなど、様々な人が集い、地域で場をひらき言葉を交わしながら、これまで語られてきた女性の身体にまつわるフィクションを検討し、3年かけてその再編、上演に向かう。
登壇者:藤原佳奈(戯曲作家、演出家)、米原晶子(NPO法人アートネットワーク・ジャパン理事長)
プレゼンテーション2
サヒヤンデ劇場・犀の角による日印国際共同制作羽衣プロジェクト
内容:2023年度から続く、3年計画の舞台作品創作プロジェクトです。長野県上田市にある民間文化施設「犀の角」と南インドケーララ州のジャングルの中に立つ「サヒヤンデ劇場」が、世界各地に残る羽衣伝説をモチーフに共同制作を行います。非都市部を拠点とする両者が「美しさ」を礎に、気候変動や戦争、コロナ後の分断などの社会課題を乗り越え、これからの世界を生きてゆく新しい価値を見出す作品を目指します。
登壇者:荒井洋文(犀の角代表、舞台芸術プロデューサー制作者)
モデレーター:稲村太郎(セゾン文化財団)
主催:公益財団法人セゾン文化財団
ヴィジティングフェローによるトーク 12/2(月)@森下スタジオ
暴力——自己防衛のための芸術的戦略についての考察

「Architectures of Violence」(2023)より nadjim bigou-fathi & soto laborによるパフォーマンス『Frsh (recherche d’objet dans une poche)』の様子
Photo: Mariana Machado
2024年10月に現代舞台芸術フェスティバル「Festival Belluard Bollwerk」(スイス・フリブール)のディレクターに就任した、エリザ・リープシュ氏によるトーク。
「私たちは日々、不可解な形の目に見えない暴力や想像を絶する恐怖に直面しています。現代は、資本主義的なネクロポリティクスが私たちの身体の生死を規定している時代です。セゾン文化財団でのレジデンスの一環として、土地、国家、国境、健康(を管理する権力)、ジェンダー、家族、国家、警察、ファシズム、ナラティブといった枠組みにおける暴力と、その展開に関するキュラトリアル・リサーチをおこないます。
私たちの身体、環境、テクノロジー、官僚主義、規範、ナラティブなどを通じて暴力を経験し続けるとき、私たちはどのように暴力と関わり、反応し、考察することができるのでしょうか。暴力はどのようなファンタジーを生み出すのでしょうか。また、時間が経っても解放や救済が得られないとき、私たちはどのような創造や表現をおこなうことができるのでしょうか。そして、自己防衛と抵抗の芸術的戦略とはどのようなものでしょうか。
ブリュッセルのBeursschouwburgでは「Architectures of Violence. 3 days on borders, fences and hijacking public space」や「In Harm’s Way. A conversation about sexual violence, self-defense and artistic strategies」を企画しました。国境を越えた連帯と一時的なコミュニティの空間構築のためのツールとしてアートを理解し、共有し、つながりを創り出すために、私のこれまでの芸術的リサーチと共同キュレーションの実践についてお話します。(エリザ・リープシュ)」
イベント概要
日時:2024年12月2日(月) 19:00-20:30
会場:森下スタジオ
登壇者:エリザ・リープシュ
※日英逐次通訳
※定員15名
※要申込
申込方法
■アーカイブ配信視聴方法
以下のフォームからお申し込みください。
Google Form:https://forms.gle/i91LZHcwUpaH8yxm9
登壇者のプロフィール等の詳細は以下をご覧ください。
https://www.saison.or.jp/vf2024_eisaliepsch
主催:公益財団法人セゾン文化財団
※「助成事業に係る広報活動やネットワーク構築」の一環として本報告会を実施します。
「次世代の芸術創造を活性化する研究助成」 2023年度助成対象事業報告会②のご案内
セゾン文化財団では、2023年度の「次世代の芸術創造を活性化する研究助成」助成対象者による研究成果や提言内容を共有する報告会を開催します。助成対象者のケアまねぶのメンバーによる活動報告と、社会デザイン領域での文化やアートの可能性を専門とする若林朋子氏をゲストに迎えたディスカッションを実施します。
本研究助成は匿名の個人の方からの当財団への寄付金を財源に開始。現代演劇や舞踊の支援、文化政策の制度や仕組みに関する現状や課題への問題意識を土台にした調査、研究を対象とし、その結果に基づいて、国や地方自治体等の公的機関や民間団体へ具体的な政策やプログラムを提案する事業を支援しています。
ケアマネジメントを用いたアーティスト支援の提言作成報告

日時:2024年9月10日(火)19:00-20:45
会場:Zoom ウェビナー
発表者:ケアまねぶ:奥山理子、タカハシ ‘タカカーン’ セイジ、長津結一郎、松岡真弥
ゲスト:若林 朋子
報告会概要
アーティスト支援に関する環境が変化し、活動を続けていくための仕組みづくりや、文化芸術関係者向けの支援窓口の設置が全国的に増えています。アーティストとオファーする側とが公正な関係性を築けているか、不均衡を是正するための働きかけも多くみられます。
「ケアまねぶ」では、アーティスト自身の顕在化した/もしくは潜在的なニーズに基づいたサポート体制の構築が求められていると考え、社会福祉の「ケアマネジメント理論」に着目。個人の「尊厳」や「自己決定」を保障し、適切なサービスの選択ができるように支援するその仕組みを、アート分野に援用する形でひとりひとりのためのケアの可能性を模索しています。
リサーチでは、アセスメント〜ケアプランの作成〜モニタリングとフィードバックを試行。2年間の3つの事例をもとに提言書をまとめました。アーティスト支援におけるケアマネジメントの実装に向けた取り組みを報告します。(ケアまねぶ)
ケアまねぶ
福祉・芸術分野の研究や実践をするメンバーによって構成されているリサーチ・コレクティブ。これまで、それぞれの現場で出会ってきた事象への問題意識をもとにして、芸術分野に広がるハラスメントの課題などに対して問題意識を共有してきた。2022年1月ごろより定期的に集まり始め、福祉制度の芸術現場への応用を模索するような議論を重ねてきた。
奥山 理子
みずのき美術館 キュレーター、Social Work / Art Conference ディレクター
2012年のみずのき美術館の開館時よりキュレーターとして企画運営を担う。2019年よりHAPSにて共生社会をテーマとした事業に参画し、福祉をはじめとする多様な分野と文化芸術をつなぐための相談事業を行っている。
タカハシ ‘タカカーン’ セイジ
一般社団法人一人一人社、すごすセンター(障害福祉サービス)運営、アーティスト、介護福祉士
障害福祉分野での表現に出会い衝撃を受け、創作支援を行う福祉現場を渡り歩きながら、並行してアート活動を行う。福祉と芸術が混ざり合う場でうまれた感動や葛藤を胸に「福祉施設」設立を願い続け、京都市内にて運営を開始したばかり。
長津 結一郎
九州大学教員[アーツマネジメント、文化政策]
多様な関係性が生まれる芸術の場に伴走/伴奏する研究者。ワークショップに関する教育、芸術作品のマネジメントやプロデュースにも関わる。著書に『舞台の上の障害者:境界から生まれる表現』(九州大学出版会、2018年)。
松岡 真弥
Mapino Front 代表、アーツオーガナイザー、キャリアサポート
身体表現のマネジメントを中心に、劇場制作、アートスペース/アートプロジェクトの事務局運営等、ジャンル横断する創作の場づくりと上演展示に携わる。現在は文化芸術に関わる人材のサポートとキャリアコンサルティングを試行中。
若林 朋子
プロジェクト・コーディネーター/立教大学大学院社会デザイン研究科特任教授
英国で文化政策を学んだのち1999~2013年企業メセナ協議会勤務。プログラム・オフィサーとして企業の文化活動や芸術支援の環境整備に従事。13年よりフリー。各種事業の企画・コーディネート、調査研究、評価、企業の社会貢献活動の開発、自治体の文化政策立案、NPOや公益法人の運営支援などを行っている。2016年より二足の草鞋で大学院教員。社会人院生と切磋琢磨しながら、社会デザイン領域で文化やアートの可能性を探る。
申込方法:ご参加をご希望の方は以下のリンクからお申込みください。
https://www.saison.or.jp/240910webinar/register
主催:公益財団法人セゾン文化財団 *「助成事業に係る広報活動やネットワーク構築」の一環として本報告会を実施します。
報告会概要については、以下のご案内をご参照ください。
-寄付プログラム-次世代の芸術創造を活性化する研究助成 2023年度助成対象事業報告会②のご案内
※広報物の一部で、当日の時間を「19:00-21:45」と表記しておりましたが、正しくは「19:00-20:45」となります。
2025年度公募プログラム オンライン説明会
はじめて申請を予定している方、久しぶりの申請を検討されている方に向けた説明会です。募集内容や申請書交付に関する概要および手続きについてご説明後、ご質問にもお答えします。
セゾン・フェローI
・8月6日(火)14:00-14:30
・8月15日(木)19:00-19:30
※上記は同様の内容ですので、いずれかをお選びください。
セゾン・フェローII
・8月6日(火)10:30-11:00
創造環境イノベーション
・9月3日(火)10:30-11:00
研究助成
・8月20日(火)17:00-17:30
海外リサーチ活動支援
・8月29日(木)19:00-19:30
お申し込み方法
以下のフォームに必要事項をご記入の上、お申し込みください。
オンライン説明会お申し込みフォーム
「次世代の芸術創造を活性化する研究助成」 2023年度助成対象事業報告会①のご案内
セゾン文化財団では、2023年度の「次世代の芸術創造を活性化する研究助成」助成対象者による研究成果や提言内容を共有する報告会を開催します。助成対象者による活動報告とともに、在住外国人の暮らしや教育、権利に精通する有識者をゲストに迎えたディスカッションを行います。
本研究助成は匿名の個人の方からの当財団への寄付金を財源に開始。現代演劇や舞踊の支援、文化政策の制度や仕組みに関する現状や課題への問題意識を土台にした調査、研究を対象とし、その結果に基づいて、国や地方自治体等の公的機関や民間団体へ具体的な政策やプログラムを提案する事業を支援しています。
長田における在住外国人の「文化権」について考察と実践を重ねた一年間の報告
日時:2024年8月7日(水)20:00-21:30
会場:Zoom ウェビナー
発表者:横堀 ふみ(NPO法人DANCE BOX プログラム・ディレクター)
ゲスト:清水 睦美(日本女子大学人間社会学部教育学科教授)
申込方法:ご参加をご希望の方は以下のリンクからお申込みください。
https://www.saison.or.jp/240807webinar/register
主催:公益財団法人セゾン文化財団
報告会概要については、以下のご案内をご参照ください。
-寄付プログラム-次世代の芸術創造を活性化する研究助成 2023年度助成対象事業報告会①のご案内
なお、2023年度の研究助成の助成対象者、ケアまねぶの報告会は2024年9月10日(火)19:00-20:45に開催予定です。
詳細は当財団のウェブサイトで後日、発表いたします。
舞台芸術活動と育児の両立について考える会
近年、当財団の助成プログラムである創造環境イノベーションや研究助成で「舞台芸術活動と育児の両立」をテーマとした申請を受けていることから、その課題への対応が喫緊であると認識し、この会を企画した。
舞台芸術活動と育児の両立についての理解やサポート体制は少しずつ進捗していながらも、まだ十分とは言えず、保護者にとって物理的にも精神的にも大きな負担になっている。
テーマに関する講義、事例報告を踏まえてその課題を取り巻く状況を明らかにし、個々の立場や経験をもとにした具体的に必要な支援を考える。
会期:2024年6-7月 全5回
会場:
第1,2,5回:オンライン
第3,4回:対面は森下スタジオ/オンラインでも開催
対象:
フリーランスで舞台芸術活動に関わる芸術家、技術者、制作者など
※育児中ではない方もご参加いただけます。
参加費:無料
定員:15名程度
※希望者多数の場合、抽選で参加者を決定します。
共同プランナー:塚口麻里子(舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM)理事長兼事務局長)
講座概要
第1回(オンライン):6/6(木)13:00-15:00
◆参加者自己紹介
◆講義:子育て支援制度の現状を知る
講師:井上美葉子(いのうえみわこ・社会保険労務士、キャリアコンサルタント、認定ワークショップデザイナー)
第2回(オンライン): 6/12(水)11:00-13:00
◆劇団、カンパニーでの取り組みの事例報告を踏まえて成果と改善点を討議
報告者:
坂本もも(プロデューサー、合同会社範宙遊泳代表、ロロ制作)
中野成樹(演出家、中野成樹+フランケンズ(なかのしげき ぷらす ふらんけんず)主宰、日本大学芸術学部演劇学科教授)
第3回:
森下スタジオ:6/22(土)13:00-15:00(子どもの同伴可、無料の託児サービス:0-12歳対象もあり)
ファシリテーター:塚口麻里子
オンライン:6/26(水)13:00-15:00
ファシリテーター:岡本純子(セゾン文化財団 シニア・プログラム・オフィサー)
※いずれかを選択してください。
◆課題の洗い出しと選定
課題例
支援団体のケア人材不足、劇場の託児サービスの課題、育児中以外の人とサポートしあえる関係の築き方、出張に必要なサポート、仕事をセーブするための支援と仕事を減らさないための支援は異なる、技術スタッフと出演者の支援は異なる、トップダウンでしかやり方を変えられないのか等。
第4回:
森下スタジオ:7/6(土)13:00-15:00(子どもの同伴可、無料の託児サービス:0-12歳対象もあり)
ファシリテーター:塚口麻里子
オンライン:7/10(水)13:00-15:00
ファシリテーター:岡本純子
※いずれかを選択してください。
◆課題についてグループディスカッション
宿題
◆具体的に必要な支援を考える。
第5回(オンライン):7/17(水)13:00-15:00
◆具体的に必要な支援の発表
申し込み:
5月16日(木)までに下記フォームよりお申し込みください。
https://www.saison.or.jp/2024childrenapply
※希望者多数の場合、抽選で参加者を決定します。
プロフィール
共同プランナー:塚口麻里子
2006年〜17年PARC – 国際舞台芸術交流センターにてTPAM in Yokohamaプログラム・オフィサーとして国際プラットフォーム事業に携わる。舞台芸術制作者オープンネットワークの設立に参加し、2013年より常務理事兼事務局長として従事。2019年4月より現職。STスポット理事。文化庁文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議委員。
第1回講師:井上美葉子
大阪・京都にて小劇場演劇や公共文化事業の制作、民間大劇場の広報・制作等を経験。現在はKYOTO EXPERIMENTのボランティア、インターンのマネジメント、ハラスメント講習の企画・運営を担当。また非常勤講師として芸術系大学、専門学校でキャリア教育に携わる。2023年より大阪アーツカウンシルアーツマネージャー。主催:公益財団法人セゾン文化財団
第2回事例報告者:
坂本もも
1988年生まれ。学生劇団から商業演劇まで幅広く制作関連の仕事を経験。舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM)、一般社団法人緊急事態舞台芸術ネットワーク(JPASN)理事。多摩美術大学 演劇舞踊デザイン学科非常勤講師。2017年に出産し育児と演劇の両立を模索中。
中野成樹
1973年、東京生まれ。2014年頃より劇団メンバーの子育てが徐々にはじまり、現在6名が育児と創作の併走を試みている。他にも、体調不良、ダブルワーク、などとも向き合う。
お問い合わせ:
公益財団法人セゾン文化財団 京橋事務所
「舞台芸術活動と育児の両立について考える会」係
Tel:03-3535-5566 Fax:03-3535-5565
website: https://www.saison.or.jp
e-mail: foundation@saison.or.jp
主催:公益財団法人セゾン文化財団
※「助成事業に係る広報活動やネットワーク構築」の一環として本会を実施します。
TOPICS カテゴリー
TOPICS 一覧
2026/01/29 2026年度フライト・グラントのご案内
フライト・グラントは、日本を拠点に活動する芸術家・制作者・舞台技術者を対象に、海外への渡航費を支援するプログラムです。
正式に招聘を受け海外で実施される本公演、コンペティションなどへの参加を支援します。
2026/01/29 ヴィジティング・フェローによるトーク 2/25(水)
インドネシア・ジョグジャカルタを拠点に活動するニア・アグスティナ氏が、日本でのリサーチをもとに、「サポートの再定義」や「ともにいること(Being Present)」の可能性について報告するトークを開催いたします。
2026/01/23 ヴィジティング・フェローによるトーク 2/5(木)
ドイツを拠点に演劇作家、パフォーマーとして活動するオリバー・ツァーン氏が、過去の作品群および、一連の新作に向けた日本での「防災」のリサーチについて紹介するトークを開催します。
2026/01/23 ヴィジティング・フェロー来日者の紹介
ヴィジティング・フェローとして、インドネシアを拠点に活動するダンス・ドラマトゥルク、プログラマー、ライターのニア・アグスティナ氏をお迎えいたします。
2026/01/23 ヴィジティング・フェロー来日者の紹介
ヴィジティング・フェローとして、ドイツを拠点に活動する演劇作家、パフォーマーのオリバー・ツァーン氏をお迎えいたします。
TOPICS アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年9月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年11月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年2月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年1月
- 2021年10月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月